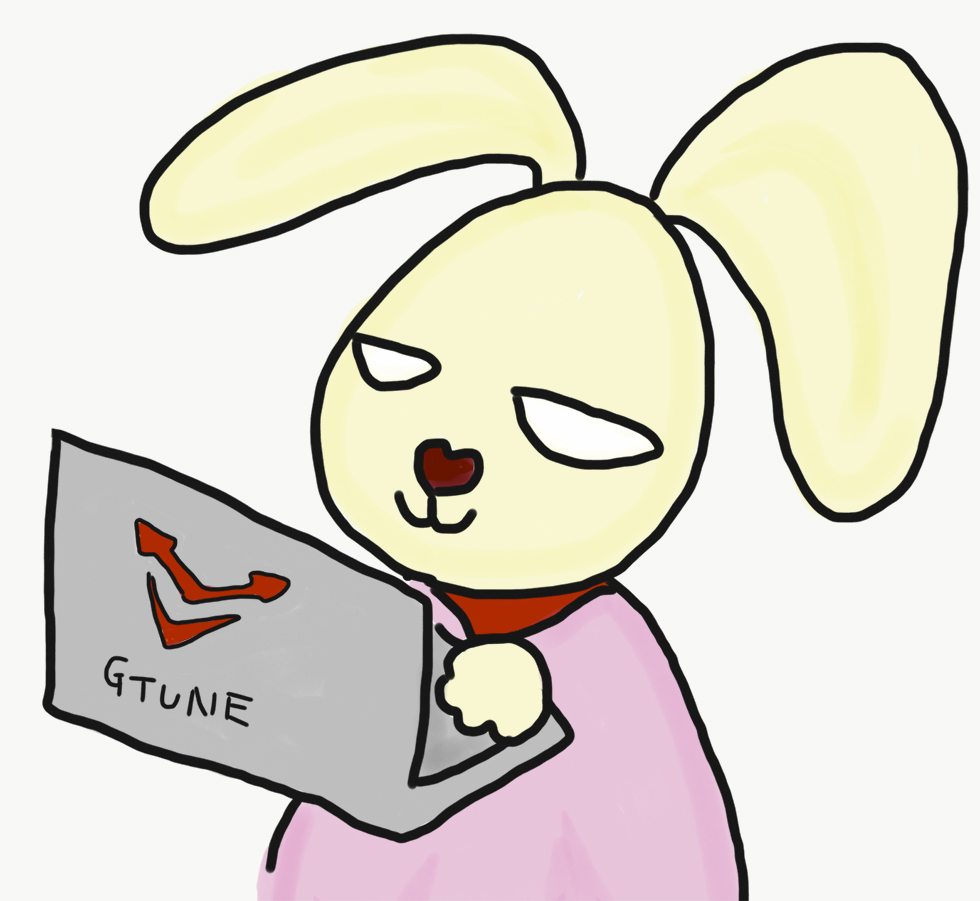
強風でグラスファイバーの折りたたみ傘が折れてしまいました。
自分で修理できないかな。
ということで、折りたたみ傘の修理を自分でやってみましたので、手順を分かりやすく紹介します。
軽くて丈夫ということで、傘、特に折りたたみ傘でグラスファイバー製の骨が増えているそうです。
最初はミスターミニットに行って修理してもらおうと思ったのですが、店員さん曰く「ウチではグラスファイバー骨の修理は扱っていません。」とのことでした。
(※扱いは店舗によって異なるかと思います。筆者の最寄りのミスターミニットの話です。)
傘の修理など一度もやったことがなかった筆者ですが、やってみたら修理完了まで20分。
思ったよりもかなり簡単だったので、傘を自分で修理する方法を共有します。
折りたたみ傘修理セットの選び方
傘を自分で修理する場合の修理セット(修理キット)は複数種類があるため、どれを購入すべきか迷うところです。
傘の骨で壊れる部分は、まわりの細い骨と中心の軸の先っぽの部分に大別されます。
まわりの細い骨を修理する人は「骨接ぎパーツ」入り、中心の軸の先っぽの部分を修理する人は
「石突・露先(傘先端パーツ)」入りの修理キットを購入しましょう。
傘修理の全パーツが揃い、とりあえずこれを買っておけば部品が不足ということがないのはこちら。
ちなみに、筆者が使ったのはこちらの↓傘修理キットですが現在売り切れのようです。
- 傘修理セット 傘リペアキット
(400円)
パーツ(部品)さえ不足しなければ、どのメーカーの傘修理セットでも修理可能です。
折りたたみ傘修理セットの中身

傘修理キットの袋を開けると・・パーツと一緒に修理マニュアルが入っています。
傘の修理セットのパーツは細かいものが多いですが、小袋に入っているので開けた途端に散らばることはありません。
修理マニュアルに従って傘の修理を開始します。
折りたたみ傘の修理を自分でやってみた
今回修理しているのは、傘の細い骨の部分です。
傘修理マニュアルの「骨継ぎパーツ」のページの説明に従って修理します。

折れた骨の部分はこんな感じです。
骨の途中がポキっと折れています。

骨継ぎ用のパーツだけ別の小袋に入っているので、パーツを探す必要はありませんでした。
骨継ぎパーツA、骨継ぎパーツB(ジョイント部が折れたとき用)、針金
が袋に入っています。
手順1:骨の曲がっている部分を、まっすぐに伸ばす

金具は、上が骨継ぎパーツB(ジョイント部が折れたとき用)で、下が骨継ぎパーツA(ジョイント部以外が折れたとき用)です。
折れているのは、ジョイント部から少しだけ下なので、AとBのどちらのパーツを使うかが微妙ですが、長さ的に骨継ぎパーツAが適当そうですのでこちらをチョイス。
手順2:骨継ぎパーツを外側からセットする
パーツを折れた骨の下に置きます。
手順3:出ている爪先しっかりと折り込んで固定する

4組ある爪のうち1組を固定したところです。
ラジオペンチ等の工具を使用して、爪を折ることで骨に金具を固定します。
ラジオペンチがすぐ見つからなかったので普通のペンチですが、作業するには何の支障もなかったです。
要は爪を折り込んで閉じられれば良いわけですからね。
ちなみに手では硬すぎて折れませんでした。
普通のペンチなのでパーツに少々傷が付きますが、ラジオペンチならもっと綺麗な仕上がりだったでしょう。

爪を2組固定したところです。
ポイントとしては、2つの爪を同時に折ってしまうこともできるのですが、必ず1枚ずつ折っていくことです。
紙を三つ折りするときのように、爪1に爪2がかぶさるように順番に折ります。

爪を4組すべて固定したところです。
これはマニュアルには書いていないのですが、4組の爪を上から順に固定するよりも、このように「1番上→4番め→2番め→3番め」と端から固定していった方が骨がふらつかず簡単ですねえ!

きれいに骨がくっつきました。
修理開始から20分、傘の骨修理の完了です!
まとめ
傘の修理はまったくはじめてだった筆者が、傘の修理を自分でやってみた報告でした!
傘の修理の専門家に修理してもらった方が美しい仕上がりであることは間違いありません。
ただ、店舗へ持ち込みが大変だったり、ファイバー骨の修理は受け付けてもらえなかったりした場合は、自分で修理は大いにアリということが分かりました。
傘の修理キットは、折れた部分によりパーツの種類が違うのでどれを購入するか少々迷います。
細い骨だけではなく傘の壊れやすい部分のパーツが、すべてパッケージされたキットならこちらです。




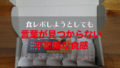
コメント